全館空調システムは電気代が高い?後悔しないためにメリット・デメリットを知っておこう

近年、住宅の断熱性や気密性を高めた高性能住宅の普及が進んでいることから、全館空調システムに関心を持っている人も増えてきたのではないでしょうか?
全館空調システムを導入することで、家のどこにいても快適な気温で過ごすことが出来る一方で、高額な導入費用が必要になるなど、メリット・デメリットの両方が存在しています。
全館空調システムの特徴を正しく理解してから導入を決めないと、「思っていたのと違った…」と後悔してしまう可能性があります。そのような後悔をしないためにも、全館空調システムの特徴、メリット・デメリットをしっかり理解しておきましょう。
全館空調システムとは?
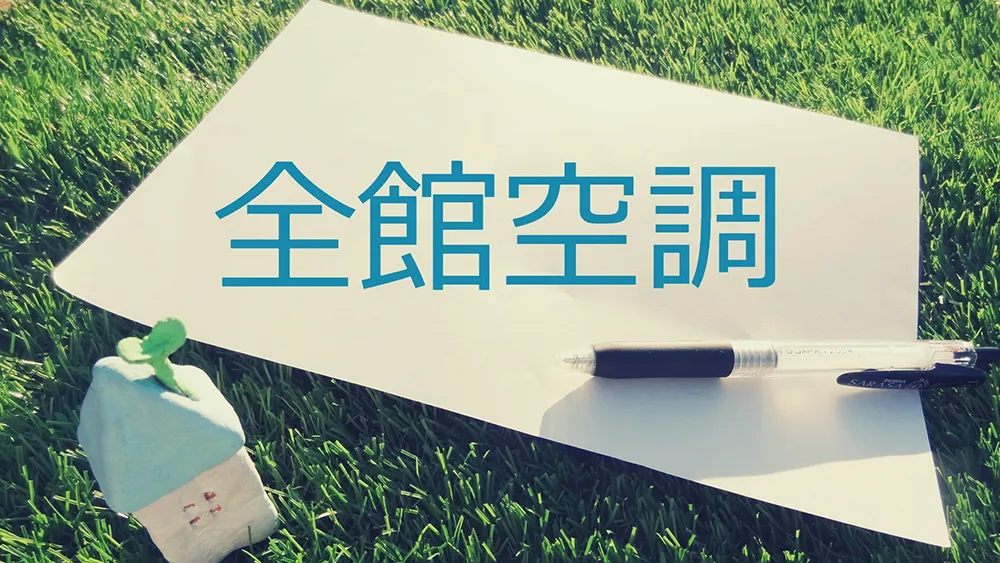
全館空調システムとは、家全体の温度を一括で管理し、家中の温度を均一に保つシステムのことを言います。従来のルームエアコンと異なり、廊下や洗面所、トイレなども含めて家全体の空調を行うため、部屋ごとの温度差を少なくすることができます。
全館空調には様々なタイプがあり、メーカーや種類によって機能や特徴が異なります。空調機の台数や機器の設置場所、冷暖房式などに違いがありますが、最近主流なのは一台の本体ユニットで冷暖房と換気を行い、各居室にダクトを用いて空気を送り込むタイプです。
このタイプの全館空調システムでは、一台の本体ユニットからパイプを通じて各部屋の空調を行います。全館空調システムで空調を行うイメージは以下のようになります。
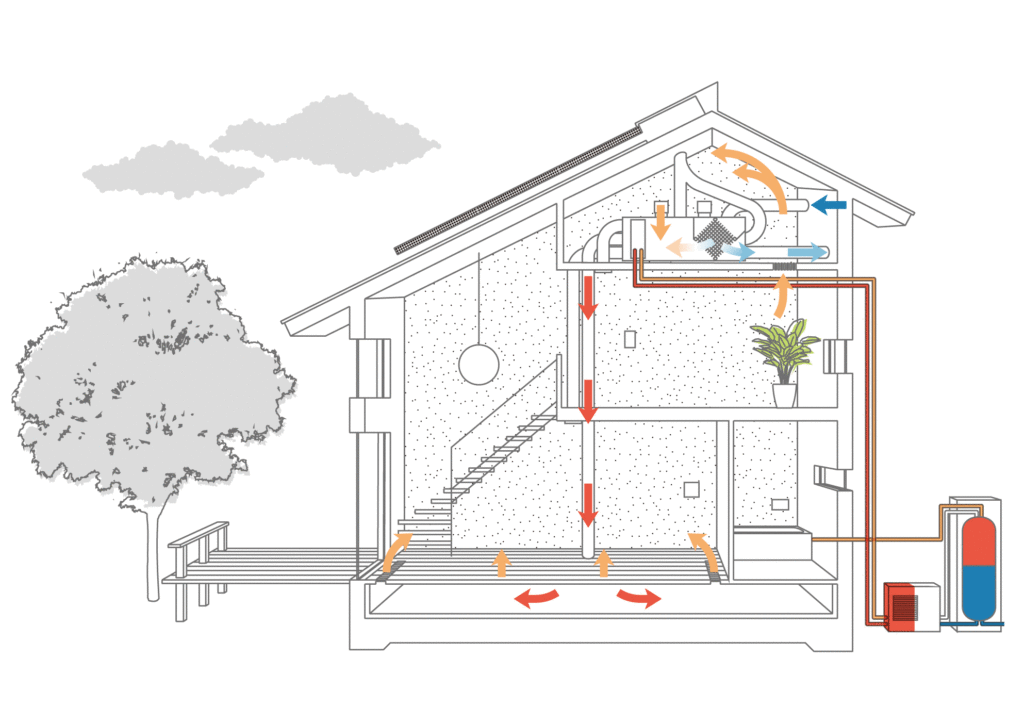
引用元:OMソーラー株式会社
住宅内部に設置された一台の本体ユニットから排出された空気が配管を経由して各居室に供給されます。1階の空気は床下を通って供給されるため、その過程で床下内部の換気も同時に行うことができます。ただし、全館空調システムのなかには天井のダクトから空気が供給され、床下内部の換気ができないタイプもあります。
室内の空気は排気ダクトから本体ユニットに戻り、本体ユニットから外部に排出されます。一台で冷暖房と換気を行うことが出来ますが、空気の流れを考慮して間取りや設計を考える必要があります。
全館空調システムのメリット

以前までは主にオフィスビル等で導入されていた全館空調システムですが、近年では戸建て住宅に導入されるケースも多く、導入率は年々高くなっていると言われています。
全館空調システムを導入する人は、どのような点に魅力を感じているのでしょうか。ここからは、全館空調システムを導入するメリットを見ていきましょう。
家の中の気温差を少なくできる
全館空調システムは、常に家全体の冷暖房を行っています。リビングや寝室だけでなく、廊下や洗面所、トイレなども含めて冷暖房を行うため、家の中の気温差を少なくすることができます。
家の中の気温差を少なくすることで、年間を通じて常に快適な住環境で生活できるメリットがあるほか、健康面でも良い効果が期待できます。
例えば、ヒートショックは急激な温度変化によって血圧が上下し、心臓や血管の疾患が起こることを言いますが、全館空調システムで気温差を少なくすることで、ヒートショックの発生リスクを軽減できる可能性があります。
キレイな空気を保つことができる
全館空調システムには、家の中の温度管理だけでなく、高性能な換気機能を持つタイプも多く存在しています。空気清浄機能や除菌機能を併せ持つタイプもあり、室内の空気をキレイに保つことが可能です。
新築住宅を建てる場合、24時間換気システムの設置が義務付けられていますが、全館空調システムに換気機能が備わっていれば24時間換気システムを設置する必要はありません。
高性能フィルターを搭載している全館空調システムを導入することで、PM2.5や花粉が家の中に侵入するのを阻止できるため、家族にアレルギー体質の人がいる場合でも安心して暮らすことができます。
室内や外観をスッキリ見せることができる
どんなにお洒落なデザインの外観に仕上げたとしても、エアコンの室外機が無造作に設置された住宅では、住宅のイメージを著しく損ねてしまうことでしょう。
全館空調は、住宅内部に設置された一台の本体ユニットからダクトを通じて各空間に空気が送り込まれるため、エアコンや室外機を設置する必要がありません。
特に和風住宅などでは、エアコンを設置することで外観やインテリアのお洒落な雰囲気を台無しにしてしまうことがあります。室内や外観にこだわりの強い人にとって、室内や外観をスッキリ見せることができるのは大きなメリットの一つと言えます。
全館空調システムのデメリット

全館空調システムを導入すると快適な住環境を手に入れられる一方で、建築コストが高額になったり、メンテナンスに費用がかかるなど、費用面のデメリットも存在しています。
また、費用面以外にもさまざまなデメリットがあるため、全館空調システムの導入を決める前にしっかり把握しておきましょう。全館空調システムのデメリットは主に以下のものがあります。
建築コストが高額になる
全館空調システムは、建物内部にダクトを通す必要があるほか、住宅の断熱性能や気密性能を高めなければならないため、一般的なルームエアコンに比べて建築コストが高額になります。
メーカーや製品によって導入費用は異なりますが、おおよそ200万円~300万円が費用がかかります。また、点検や部品交換にかかるメンテナンス費用も把握しておかなければなりません。特にダクトの清掃時に分解整備をしなければならず、清掃費用が高額になる可能性があります。
さらに、全館空調システムを導入するためには、本体ユニットを設置するスペースを用意したり、空気の流れを考慮した設計が求められるほか、基礎断熱工法を用いるなどの工夫が必要となるため、設計料も高額にある可能性があるので注意しましょう。
部屋ごとの空調が難しい
全館空調システムは一台の本体ユニットで空調を行うため、部屋ごとの温度設定を行えないケースがほとんどです。人によって快適な温度が異なる場合には、家族全員が心地よく過ごせない可能性があります。
家族の中に、寒がりな人と暑がりな人がいる場合には、少し価格が高くなりますが、部屋ごとの温度設定が可能な全館空調システムを選ぶようにしましょう。
ニオイが家全体に広がる
住宅内部の空気は排気ダクトから本体ユニットを経由して外部に排出されますが、一部の空気は循環して再び各部屋に給気されることになります。そのためペット部屋やゴミ置き場の匂いが、家中に行き渡る恐れがある点に注意しましょう。
全館空調システムのなかには消臭機能が備わっているタイプも存在していますが、特に強い匂いが発生しやすい場所には、別で換気システムを設置するなどの対策が求められます。
空気が乾燥しやすい
全館空調システムを導入した住宅では常に空調と換気が行われるため、空気が乾燥しやすくなります。住宅内部の空気が乾燥すると風邪にかかりやすくなったり、乾燥肌などの健康被害リスクが高くなってしまいます。
人が快適に感じる湿度は夏場で50%~60%、冬場で40%~50%とされています。湿気の高い夏場は全館空調システムによって湿度を下げてくれますが、逆に空気が乾燥しやすい冬場は加湿器などを活用して湿度調整をする必要があります。
全館空調システムの電気代は高い?

全館空調システムに関する口コミを見ていると「電気代が高くなった…。」といった口コミを多く見かけます。そのため、実際にどのくらい高くなるか気になっている人も多いでしょう。
エアコンにかかる電気代は、エアコンの種類や稼働状況によって大きく変動するため正確な数値を算出することは出来ませんが、一般的な数値を元に電気代の比較を行うとともに、電気代を節約するポイントなどを解説していきます。
エアコンの電気代の比較
4LDKの戸建て住宅を例に比較をしていきます。同条件で比較するために電気代は1kWhあたり31円で計算し、24時間・365日稼働した場合の比較を行っていきましょう。
エアコンの電気代
リビングに20畳用を一台、各居室に6畳用を1台ずつ設置した場合の電気代を算出します。20畳用の消費電力は年間約1,900kw、6畳用は年間約700kwhとします。
1,900kwh × 31円 = 58,900円
700kwh × 31円 × 4台 = 86,800円
リビングと各居室を合わせると「年間145,700円」の電気代がかかる計算です。実際は使用時間や外気温度によって金額は異なりますが、20畳用のエアコンを1台、6畳用のエアコンを4台、24時間・365日稼働させた場合の電気代の目安のこのようになります。
全館空調の電気代
全館空調システムの消費電力はメーカーや商品によって大きく異なり、年間約3,000kw~7,000kwの電力を消費するとされています。全館空調システムの年間電気代の目安は以下のとおりです。
93,000円 ~ 217,000円
全館空調システムの電気代には換気にかかる電力も含まれていることを考えると、ルームエアコンと比べてもそれほど大きな違いがないことが分かります。
空調にかかる電気代は住宅の断熱性能や気密性能、気温や気候など様々な条件に左右されますが、全館空調システムの性能や使い方次第では、エアコンよりも電気代が安くなる可能性もあるでしょう。
全館空調システムの電気代が高いと言われる理由
それほど違いがないように見える全館空調システムとルームエアコンの電気代ですが、なぜ全館空調システムの電気代は高いと言われているのでしょうか。その理由には主に以下の3つが挙げられます。
家全体の冷暖房を行うため
全館空調システムは、家全体の空調を同時に行ないます。各部屋ごとに温度設定は出来ても、電源のON/OFFを切り替えることが出来ないため、使っていない部屋の空調も行うことになります。
就寝時以外は寝室を使用することがない家族であれば、日常的に使うエアコンはリビングのみの稼働で済みますが、全館空調システムは常に家全体を冷暖房するため、電気代が高くなると考えられます。
稼働時間が長くなってしまうため
最近は電気料金が高騰しており、電気代を節約するために睡眠時はエアコンをOFFにする人も多いと思いますが、全館空調システムは家族の誰か一人が使用していると、家全体の冷暖房が行われます。
全館空調システムは各部屋ごとに電源のON/OFFを行うことが出来ないため、どうしてもシステムの稼働時間が長くなってしまい、電気代が高くなってしまうことが考えられます。
マンションから戸建て住宅に引っ越したため
全館空調システムやエアコンの違いに関わらず、戸建て住宅はマンションと比べて空調にかかる電気代が高くなるとされています。その大きな原因は建物構造の違いによります。
マンションの多くは鉄筋コンクリート造ですが、戸建て住宅の大半は木造で建てられています。鉄筋コンクリート造は木造と比べて断熱性能・気密性能が高く、冷暖房効率が高いという特徴を持っています。また、マンションの角部屋を除き、マンションの部屋は二面しか外気に触れないため、外気温の影響を受けにくくなります。
木造の戸建て住宅の性能をどれだけ高めたとしても、構造の性質上、どうしても鉄筋コンクリート造のマンションと比べると断熱性能や気密性能は劣ってしまうため、電気代は高くなる傾向にあります。
全館空調システムの電気代を節約するポイント
全館空調システムは導入に高額な費用がかかるとともに、使い方によっては毎月の光熱費も高くついてしまうため、少しでも電気代を節約したいと考えている人も多いでしょう。そこで、全館空調システムの電気代を節約するためのポイントをいくつかご紹介します。
運転停止機能を使用する
空調を行う場合、室内温度と設定温度の差が大きい運転開始時が最も消費電力が大きくなるため、短時間のうちに電源のON/OFFを繰り返さない方が良いとされています。そのため全館空調システムのメーカーの多くは、24時間稼働を推奨しています。
ただし、一定時間以上外出する場合は、運転停止機能を使って運転を停止させた方が消費電力が少なくて済みます。目安としては、外出時間が2時間以上になる場合は運転を停止させた方が良いでしょう。
風量設定を自動運転にする
全館空調システムには、自分で風量の強弱を設定する方法以外に、設定温度と現在の室内温度に応じて自動で風量を調整してくれる機能が備わっています。電気代を節約しようとして風量を「弱」にすると、室内が設定温度に達するまでに時間がかかり、逆に冷暖房効率を下げてしまいます。
風量設定を自動運転にすることで、設定温度と室内温度の差を感知し、効率良く設定温度に達する風量に調整してくれます。設定温度に達した後も、最も冷暖房効率の良い風量をキープするため、風量設定は自動運転にしておきましょう。
換気の方法に気を付ける
室内の空気が排出されることで、再び温度を調整するための送風が多く行われて消費電力が大きくなってしまうため、窓の開けっぱなしやキッチン換気扇の動作には気を付けましょう。
24時間換気システムを別で設置している場合、そこから常に空気が排出されて空調にかかる消費電力を大きくしてしまう可能性があります。特に排気のみを機械式に行う第3種換気が設置されている場合には、外に排出される空気量が多くなるため注意が必要です。
冬は加湿器を併用する
人間が感じる体感温度は湿度が深く関わっており、気温が低くても湿度が高いと暖かく感じます。同じ気温であっても、湿度が異なる場合は湿度が高い方が体感温度が高くなるため、室内の湿度を高めることで低い気温でも快適な温度に感じることができます。
人が快適に感じる湿度は夏場で50%~60%、冬場で40%~50%とされています。乾燥しやすい冬の季節は加湿器を上図に使って、快適な湿度を保つように心がけましょう。
全館空調で後悔しないための注意点

全館空調システムを導入する場合は、設計時点から気を付けなければいけない点がいくつか存在しています。将来的に後悔してしまわないように、注意点をしっかり把握しておきましょう。
高気密高断熱住宅の仕様にする
気密性の低い住宅では、家中の隙間から室内と外部の空気が出入りしやすくなることから、室温を一定に保ちにくくなり、空調にかかる消費電力が大きくなってしまいます。そのため、C値1.0を下回る気密性能を確保することが望ましいとされています。
また、住宅の断熱性能が低いと、室内温度が外部気温の影響を受けやすくなり、冷暖房効率が低下してしまいます。常に快適な室内を保ちながら消費電力を節約するためには、HEAT20で定められたG2ランクもしくは断熱等級6以上を確保するようにしましょう。
高気密高断熱住宅については別記事で詳しく解説しているので、そちらの記事も併せてお読みください。

ダクトに抵抗をかけない設計を心掛ける
全館空調システムはダクトを経由して各部屋に送風されるため、ダクトが無理な角度に曲がっていたり、とぐろを巻いて余分な抵抗がかかっていると、送風の妨げになってしまいます。
送風量が減ると空調が効きにくくなり、強風運転を続けることで消費電力の増大に繋がります。なるべくダクトに抵抗をかけないように、設計段階で入念な打ち合わせを行うようにしましょう。
ニオイ対策をしっかり行う
全館空調システムは一台の本体ユニットを経由して給気と換気を行うため、ニオイ対策が施されていないとキッチンやダイニングのニオイが家全体に広がってしまう可能性があります。
このようなニオイ問題を解決するために、ニオイが発生しやすいキッチン・ダイニング・生ゴミ置き場などには24時間換気システムを導入するのが良いでしょう。
24時間換気システムにはいくつか種類がありますが、全熱交換型第一種換気を選ぶことで、排気される空気から熱や湿気を取り出し、給気される空気に移すことができるため、室内温度や湿度を一定に保つことが可能です。
室内での喫煙は控える
家族のなかに喫煙者がいる場合には、室内での喫煙は控えるようにしましょう。室内で喫煙すると煙が混じった空気が各部屋に流れるだけでなく、ダクト内部にヤニが付着しニオイの原因となります。
全館空調システムのダクトは住宅内部を通っているため、ダクト内部の清掃は一苦労です。ダクト自体を交換するのも現実的ではないため、家の中ではタバコは吸わないようにしましょう。
将来的なメンテナンス費用を把握しておく
全館空調システムは、一般的なルームエアコンと比べて施工や構造が複雑なことから、維持管理に伴うメンテナンス費用が高くなる傾向にあります。どんなに丈夫な設備機器であっても15年前後で修理や交換が必要になるため、修理や交換にどの程度の費用がかかるのかを把握しておくことが重要です。
ハウスメーカーや工務店独自でアフターサービスを行っている会社もあるため、そのような建築会社を選ぶのも重要です。また、全館空調システムのメーカー保証の内容もしっかり把握しておきましょう。
まとめ
この記事では、全館空調システムの特徴やメリット・デメリット、年間でかかる電気代の目安や節安するためのポイントにくわえ、全館空調システムを導入する際の注意点などについて解説しました。
全館空調システムには多くの種類がありますが、最近主流のタイプでは一台の本体ユニットからダクトを経由して家全体の冷暖房と換気を行う事で、室内や外観をスッキリ見せ、家の中の気温差を少なくしてキレイな空気を保ち、快適な住環境を保つことができる一方で、部屋ごとの空調が難しく、ニオイや乾燥に悩まされる可能性があるとともに、建築コストが高くなってしまう傾向にあります。
また、新築戸建てに全館空調システムを導入する際には、高気密高断熱住宅の仕様が必須であり、ダクトの取り回しや冷暖房効率を考えた設計が求められることから、全館空調システムの施工に詳しいハウスメーカーや工務店に工事を依頼することが重要と言えるでしょう。
















