失敗しないハウスメーカーの選び方|注文住宅メーカーの比較ポイント、入居までの流れ

注文住宅を建てたいけど、「ハウスメーカーが多すぎて決められない…」と悩んではいないでしょうか?ハウスメーカーは日本全国で数多く存在しており、どの会社に依頼すれば良いのか分からずに困っている人も多いはずです。
地元の工務店も含めると、選択肢は数万社にのぼります。自分に合ったハウスメーカーを選ぶためには、ハウスメーカーごとの特徴や違い、比較すべきポイントを理解しておくことが重要です。
この記事では、家づくりを失敗しないためのハウスメーカー選び方、ハウスメーカーの選ぶ際の比較ポイントや入居までの流れを解説します。
ハウスメーカーと工務店はどう違う?

どのハウスメーカーに建築を依頼するかを考える前に、ハウスメーカーと工務店の違いを理解しておきましょう。ハウスメーカーと工務店の特徴をまとめると以下のようになります。
| ハウスメーカー | 工務店 | |
|---|---|---|
| 施工エリア・規模 | 全国規模で従業員数が多く、対応できる範囲が広い。 | 地域密着型で従業員数が少なく、対応できる範囲が狭い。 |
| プランの自由度 | あらかじめプランが用意されており、自由度が低い。 | 自由度が高く、間取りや住宅設備を自分好みに決められる。 |
| 施工の精度・品質 | 建築資材の加工を工場等で行うため、品質が安定している。 | 現場で加工するため、職人の腕次第では施工の精度が低い場合がある。 |
| コスト・価格帯 | 広告費や人件費に多くのコストを費やすため、価格が高い。 | 広告費や人件費にコストをあまりかけていないため、価格が安い |
| 工期 | 現場では建築資材を組み立てるだけのため、短い工期で施工が可能。 | 建築資材を現場で加工していくため、職人次第で工期が長くなる。 |
| アフターメンテナンス | 社内マニュアルが徹底され、アフターメンテナンスが充実。倒産リスクも低い。 | 人手が足りず、アフターメンテナンスがおろそかになる可能性がある。 |
上記の表はあくまで全体的な傾向を示すものです。最近では全国展開しているハウスメーカーの中にも、ローコストやプランの自由度を強みにしている会社も多く存在しています。
また、工務店の中にも、住宅展示場にモデルハウスを用意したり、コンセプトプランやシリーズを用意してマニュアル化を図っている中堅ビルダーも存在しており、ハウスメーカーと工務店の明確な違いが分かりづらくなってきています。あまりハウスメーカーと工務店の区別にとらわれず、会社ごとの商品力や特徴を分析して依頼する会社を選ぶことが重要と言えるでしょう。
ハウスメーカーのタイプ別の特徴
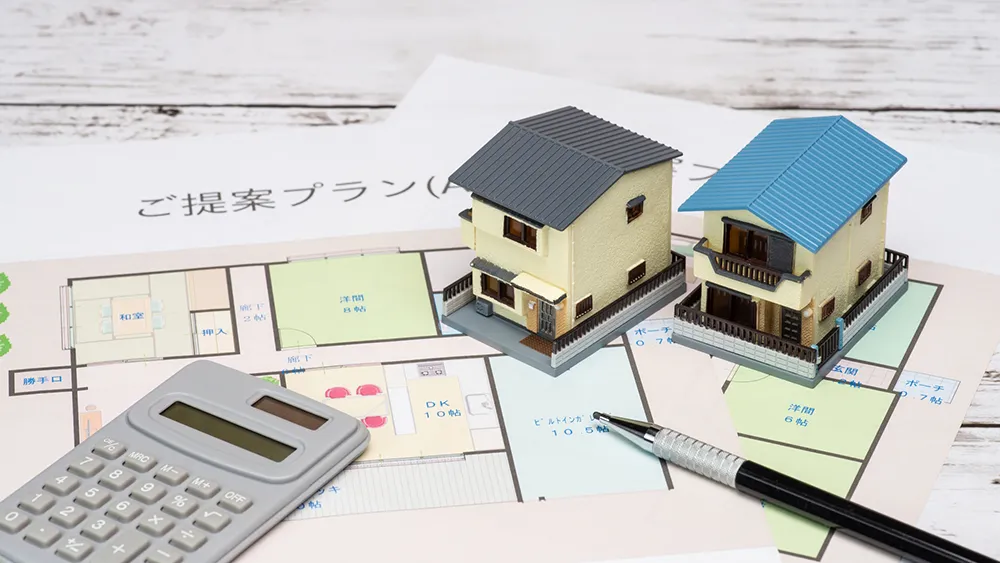
日本全国で数万社あるハウスメーカーですが、「ハイブランド型」「住宅性能重視型」「ローコスト型」「バランス型」の4タイプに分類できます。ハウスメーカーをタイプ別に絞り込むことで、効率的に自分に合ったハウスメーカーを選ぶことが可能です。
注文住宅で失敗しないためには「予算」と「希望」の両方を満たすハウスメーカーを選ぶ必要があります。どんなにオシャレで高性能の家に住んでいても、毎月の支払いが困難では安心して生活を続けることはできないため、まずは注文住宅に充てられる予算を明確にすることが重要です。
予算が明確になったら、自分がマイホームに求める条件に優先順位を付けていきます。「デザイン性」「住宅性能」「価格」など、優先したい項目を明確にし、その項目に沿ったタイプに絞り込んでハウスメーカーを探していきましょう。
高級志向の人向け「ハイブランド型」
予算に余裕があり、高級感のあるデザイン性の高い家に住みたい人にはハイブランド型のハウスメーカーがおすすめです。ハイブランド型のハウスメーカーは、家づくりの長い歴史と実績があり、経営基盤がしっかりしていて倒産の心配もなく安心感があります。
専属の設計士やデザイナーがつき、自分の好みをしっかり把握した上でエグゼクティブな提案をしてくれるなど、VIP対応が徹底されています。世間の認知度も高いため、ブランド住宅として周囲にアピールできます。
代表的なハイブランド型のハウスメーカーとしては以下のハウスメーカーが挙げられます。
- 積水ハウス
- 三井ホーム
- スウェーデンハウス
- ヘーベルハウス
- 住友林業
- 大和ハウス
- ミサワホーム
ハイブランド型ハウスメーカーでは、建築費用が高い分、デザイン性や住宅性能に優れ、自由度が高く自分の好みを反映したマイホームを建てることができます。
住宅性能にこだわる人向け「住宅性能重視型」
住宅には断熱性・気密性・耐震性など様々な性能が求められます。家づくりにおいて、それらの住宅性能にこだわりたい人には住宅性能重視型のハウスメーカーがおすすめです。住宅性能重視型のハウスメーカーは、高性能な分価格も高くなりますが、年中を通じて快適に過ごすことができ、地震等の災害時にも倒壊リスクが低く安心です。
日本には四季があり、住宅を取り巻く環境は常に変化します。夏には暑さと湿気で部材は膨張し、冬には寒さと乾燥で部材は収縮するため、住宅の耐久性を高めるには住宅内部と外部の空気と熱を遮断する「断熱性」と「気密性」の向上が必要となります。また、台風や地震といった自然災害の発生も多く、「耐震性」や「耐風性」を高めることも重要です。住宅性能重視型のハウスメーカーでは、それらの住宅性能が高いマイホームを建てることができます。
代表的な住宅性能重視型のハウスメーカーとしては以下のハウスメーカーが挙げられます。
- 一条工務店
- アキュラホーム
- セキスイハイム
- トヨタホーム
- パナソニックホームズ
断熱性や気密性を高めることで室内が外気温の影響を受けにくくなるため、年間を通じて快適な住環境で過ごすことができる上に、エアコン等にかかるエネルギーを削減して毎月の光熱費を節約する効果も期待できます。
なお、住宅性能を示す指標としては、住宅性能表示制度が定める評価基準が多く用いられています。住宅性能表示制度については別記事で詳しく解説しているのでそちらをご参考ください。

価格の安さを重視する人向け「ローコスト型」
マイホームの建築に充てられる予算が限られており、価格の安さを重視したい人にはローコスト型ハウスメーカーがおすすめです。ローコスト型ハウスメーカーでは、トレンドを抑えたデザインの家を低価格で建てることができます。
ローコスト型ハウスメーカーの多くでセミオーダータイプが採用されており、いくつかの決まったパターンから間取りや住宅設備を選ぶことになります。他タイプのハウスメーカーと比べて打ち合わせにかかる時間が短いため、建物に対してそれほどこだわりがなく「とにかく早く、安くマイホームを建てたい!」という人に向いています。
代表的なローコスト型ハウスメーカーとしては以下のハウスメーカーが挙げられます。
- タマホーム
- 秀光ビルド
- 飯田グループHD
- オープンハウス
ローコスト型ハウスメーカーでも、オプション対応で「耐震性」や「断熱性」を高めてくれる場合があります。どこまでが標準価格に含まれているかはハウスメーカーによって異なるため、標準仕様の範囲を事前に確認しておくことが重要です。
バランスを重視する人向け「バランス型」
デザイン・性能・価格など、全体的なバランスを重視したい人にはバランス型ハウスメーカーがおすすめです。バランス型ハウスメーカーでは、トレンドを抑えたデザインかつ重要度の高い住宅性能を有した住宅をコスパ良く建てることができます。
バランス型ハウスメーカーの数は全タイプの中で最も多く、どの会社にすべきか悩むかもしれません。ハウスメーカーごとに重要視するポイントが異なるため、自分のこだわりとマッチするハウスメーカーを選ぶ必要があります。
代表的なバランス型ハウスメーカーとしては以下のハウスメーカーが挙げられます。
- アイダ設計
- 無印の家
- アエラホーム
- アイ工務店
- ヤマト住建
- クレバリーホーム
バランス型ハウスメーカーでは、予算に合わせて幅広い住宅モデルが用意されています。住宅性能重視型と同等の性能を持った住宅を建てるハウスメーカーや、完全自由設計で対応してくれるハウスメーカーなど様々なため、自分の希望を明確にした上でハウスメーカーを選ぶことが重要です。
ハウスメーカー選びの比較ポイント

マイホームに求める優先順位が決まり、ある程度ハウスメーカーの方向性が決まってきたら、実際に複数社に絞り込んで具体的な比較を行っていく必要があります。しかし、初めてハウスメーカー選びをする人にとっては「どのようなポイントを比較すれば良いか分からない…」と悩む場合もあるでしょう。
ハウスメーカーを選ぶ際は、どのような点を比較すれば良いのでしょうか。ここからは、ハウスメーカー選びの比較ポイントを7つ紹介します。
エリア
知名度の高いハウスメーカーでは日本全国の幅広いエリアに対応していますが、ハウスメーカーによっては、寒冷地帯、温暖地帯等は苦手としている場合があります。また、そもそも対応していない可能性も考えられます。
お気に入りのハウスメーカーを選んだとしても、建設予定地が対応エリア外だとそのハウスメーカーで家を建てることはできません。対応エリアはWEBサイト等で確認できるため、事前に確認しておくようにしましょう。
構造・工法
住宅の構造には、大きく分けて「木造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」の3つがあり、その中でも様々な工法が存在しています。構造・工法は、住宅において重要な要素のため、ハウスメーカーごとの構造・工法を把握しておくことが重要です。
ハウスメーカーによっては独自の構造・工法を採用している場合もありますが、代表的な構造・工法は以下の7つが挙げられます。
| 構造・工法 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 木造 | 木造軸組工法(在来工法) | 日本の伝統的な工法で柱・梁・筋交いで構成される |
| 木造枠組工法(2×4工法) | 2×4インチあるいは2×6インチの角材を使用して組み立てる | |
| 木質系プレハブ工法 | 工場で作られたパネル状の木材を組み立てる | |
| 鉄骨造 | 軽量鉄骨構造 | 厚さ6mm未満の鋼材が使われている |
| 重量鉄骨構造 | 厚さ6mm以上の鋼材が使われている | |
| 鉄骨系プレハブ工法 | 鉄骨の軸組みに工場で作られた部材を組み立てる | |
| 鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート構造 | 鉄筋にコンクリートを流し込んで形成する |
上記の7つの構造・工法を基準として、ハウスメーカーごとに改良を重ねた独自の構造・工法が採用されています。構造・工法や住宅の耐久性やプランの自由度に大きく影響を与えるため、ハウスメーカーが採用している構造・工法をしっかり比較しておきましょう。
デザイン
せっかく注文住宅で家を建てるなら、自分好みのデザインで家を建てたいと思う人がほとんどでしょう。シンプルモダン・和モダン・アメリカンスタイル・ヨーロピアンスタイル等、多くのデザインが存在しています。
特定のデザインを得意とするハウスメーカーもあれば、様々なデザインに対応できるハウスメーカーもあります。ハウスメーカーごとに得意としているデザインは異なるため、自分の好みに合うデザインの住宅を建ててくれるか十分に検討する必要があります。
また、外観や内装のデザインは素材や色を変えるだけで大きくイメージが変わるため、自分が好きな素材や色を選べるかどうかも含めて検討するようにしましょう。
価格・費用
家づくりにおいて、予算を考えない人は少ないはずです。自分の建てたい家が予算内におさまるかどうかは、ハウスメーカーを選ぶ際の重要な判断項目の一つと言えます。
ハウスメーカーによって費用の相場は異なります。自分の希望をしっかり伝え、複数のハウスメーカーから見積もりを取って比較をすることが重要です。単純に標準仕様の坪単価だけで比較するのではなく、「こだわりたい箇所」と「削ってもいい箇所」を整理して、自分が建てたい家の詳細を把握してから価格を比べるようにしましょう。
住宅性能
耐震性や耐久性は、長い間安心して住み続けられるマイホームを建てるために抑えておきたいポイントと言えます。また、年中を通じて快適に過ごすには、断熱性や気密性を高めることも重要です。ハウスメーカーごとに住宅性能は異なるため、自分が重要視している住宅性能を有しているかを確認しておきましょう。
住宅性能を示す指標にはあらゆるものが用意されていますが、分かりやすい指標としては住宅性能表示制度が有名です。各性能を等級で表すことで、住宅に詳しくない消費者でも簡単に住宅性能を理解できるようになっています。住宅性能表示制度は多くのハウスメーカーで採用されており、各性能の等級はハウスメーカーのホームページやカタログで確認できるようになっています。
また、住宅の断熱性能を示す指標としては、最近では「HEAT20」が注目を集めています。国が定める断熱性能の基準よりも厳しい基準が設けられているため、断熱性にこだわる人は参考にしたい指標と言えるでしょう。HEAT20については別記事で詳しく解説しているのでそちらをご参考ください。

保証・アフターサービス
どれほど耐久性が高い住宅であっても、時間が経つにつれてメンテナンスが必要となるため、各ハウスメーカーは保証やアフターサービスに独自の基準を定めています。
一定期間の定期メンテナンスを無料で対応してくれるほか、万が一不具合が生じた場合には24時間対応可能なハウスメーカーもあるため、ハウスメーカーごとの保証やアフターサービスの内容を比較しておくことが重要です。
また、法令での最低保証期間は10年と定められていますが、ハウスメーカによっては30年保証や60年保証が設けられている場合があります。その場合、ハウスメーカー指定の工務店で定期的にメンテナンスを実施しなければならないケースが多くなっているため、保証の適用条件についても確認しておく必要があります。
営業担当者の人柄
注文住宅を建てる際、ハウスメーカーの営業担当者と数カ月、長い場合は1年以上も打ち合わせを重ねていくことになります。営業担当者の人柄や相性が悪いと、ストレスを感じながらの家づくりになってしまい、良い家づくりをすることは難しくなってしまうでしょう。
どれだけ良い建物を建てるハウスメーカーであっても、営業担当者の対応次第では家づくりが悪い思い出になってしまう可能性もあります。失敗しない家づくりを実現するためには、信頼できる営業担当者がいるハウスメーカーを選ぶことが重要です。
ハウスメーカー選び~入居までの流れ

注文住宅でマイホームを建てる場合、検討を始めてから引越しまでに1年近くかかるとされています。その期間に様々なステップを踏む必要があるため、なるべく早い段階で注文住宅の流れを理解しておくことが重要です。
全体の流れを理解することで、「今すべきことは何か?」「無理のないスケジュール管理が出来ているか?」といったことを把握しやすくなります。注文住宅をスムーズに進めるために、しっかりと全体の流れを理解しておきましょう。
ここからは、注文住宅の全体的な流れや各ステップの注意点等を解説していきます。
①マイホームの総予算を決める
まずは、マイホームの購入に充てられる全体の予算を計算していきます。一般的な予算の計算方法としては、用意している自己資金の金額と、住宅ローンで借りられる金額を元に計算します。ただし、住宅ローンで借りられる金額はあくまで「世帯年収」で算出されるため、実際に長期間返済できる借入額かどうかはしっかり検討する必要があります。
同じ年収であっても、夫婦だけの2人家族と、夫婦と子供3人の5人家族では当然支出が変わってきますが、借りられる金額は同じとなるため、安易に予算を決めるのではなく、実際の収入と支出のバランスを考慮して予算を計算するようにしましょう。
なお、新築戸建てを購入する際の費用としては、「土地代」「建物代」「諸費用」の3種類があります。これらの費用については別記事で詳しく解説しているのでそちらをご参考ください。

②理想の住宅のイメージを明確にする
自分が住みたい理想の住宅のイメージを明確にすることで、どのようなハウスメーカーに依頼すれば良いかの判断がしやすくなります。以下の点などを明確にしていきましょう。
- 立地(建築場所)
- 住宅性能
- 大きさ・広さ
- 希望する間取り
- デザイン
- 将来的なビジョン
- 重要視したいポイント
最近ではSNSやホームページで、様々なハウスメーカーが建てた住宅を見ることが出来ます。あらゆるメディアから情報収集を行い、理想の住宅のイメージを明確にしていきましょう。
③ハウスメーカーを2~3社に絞り込む
自分が住みたい理想の住宅を建てるハウスメーカーを探し、ハウスメーカーを2~3社に絞り込みます。多くのハウスメーカーではモデルハウスを用意しているため、実際に展示場に足を運んで、実物を確認することができます。
ただし、モデルハウスはオプション仕様になっている場合も多く、モデルハウスと同等の建物を建てる場合は予算を大きく上回ってしまう可能性があるため、自分の希望をしっかりと担当者に伝え、新築に要する大体の予算を把握しておくことが重要です。
④土地と建物の予算の割合を決める
マイホームの価格は、土地代と建物代の双方で成り立っています。新築を依頼するハウスメーカーを絞り込むことで、建物代の目安を把握できるため、土地代の予算を算出することができます。
土地予算 = 総予算 – 建物予算 – 諸費用
土地にはエリアごとに一定の相場が存在しているため、算出した土地予算が、自分が探しているエリアの相場とかけ離れていないかを検討することも重要です。万が一土地予算が安すぎる場合には、「依頼するハウスメーカーを変更する」「建てる建物の大きさや仕様を変更する」「土地を探すエリアを変更する」等の対応が必要となります。
⑤マイホームを建てる土地を探す
マイホームを建てる土地を持っていない人は、土地を探す必要があります。土地を探す方法はいくつかあるため、自分に合った方法で土地を探しましょう。
土地探しのコツや方法は、こちらの記事で詳しく解説していますのでご参考下さい。

⑥間取りプラン作成・見積もり
気に入った土地を見つけたら、ハウスメーカー各社に間取りプランの作成を依頼しましょう。エリアによっては建物の建築に対する制限が厳しく、希望の間取りプランが入らない可能性があるため、必ず土地ごとに間取りプランを作成してもらうことが重要です。
また、前面道路の幅員や土地形状、道路との高低差や近隣状況など、様々な要因によって建築費用も変わってくるため、見積もりと併せて提案を受けるようにしましょう。
⑦住宅ローン事前審査
住宅ローンを利用する人は、住宅ローンの事前審査を申請する必要があります。住宅ローンの事前審査は、土地代と建物代が決まり、マイホーム購入に要する資金が明確になった時点で行うのが一般的です。
住宅ローンの事前審査を申請する方法は、以下の3通りがあります。
- 自分で行う方法
- 土地を担当する不動産会社経由で行う方法
- 建築を依頼するハウスメーカー経由で行う方法
基本的に誰から申し込んでも住宅ローンの金利等の条件に変動はないため、不動産会社やハウスメーカーに手続きを任せた方が手間を省くことができます。
ただし、最近利用者が増えているネット銀行では、自分自身で申請手続きや窓口との対応をしなければいけません。ネット銀行を利用する場合には、各所との調整にミスが起きないよう注意しましょう。
⑧土地の売買契約・工事請負契約
事前審査の内諾が下り、土地の購入・建築の依頼を決めたら土地の売買契約と工事請負契約を締結します。契約書には、契約内容やキャンセル時のルール等、多くの内容が記載されています。
契約後にトラブルにならないためにも、契約書に書かれている内容をしっかり確認して契約を締結することが重要です。もし書かれている内容が理解できない場合は、担当者に確認を取るようにしましょう。
⑨住宅ローン本審査
住宅ローンの本審査には、契約締結後の土地の売買契約書と工事請負契約書の提出が必要となるため、各契約が完了してから住宅ローンの本審査を申請します。
本審査は事前審査と比べて必要書類が多く、所得証明書や住民票等の公的書類が必要となります。審査に要する期間も長く、約1週間~2週間ほどかかるのが一般的です。
⑩詳細打ち合わせ・建物プランの確定
建築確認の申請に向けて、具体的なプランや仕様を決めるための打ち合わせを行います。窓の配置やサッシの色決め等の他、オプション追加を行う場合には資金計画の調整をしていきます。
具体的なプランが決まり、建築確認を申請した後は間取りの変更が難しくなります。また、建築確認が下りてからの変更は、変更に時間がかかり工期が遅れる原因となります。
ハウスメーカーによっては、プラン確定後の変更には費用を請求される場合もあります。間取りや仕様で後悔しないために、十分に検討してから建物プランを確定しましょう。
⑪土地の引き渡し・着工
住宅ローンの本審査が無事通り、金融機関との金銭消費貸借契約を締結したら、土地の引き渡しを行います。土地の引き渡しは住宅ローンを借り入れる銀行の店舗で行うのが一般的です。
土地の引き渡しを終え、土地が自分の所有物になったらいよいよ着工です。土地に古家が建っている場合は、建物を解体してから新築工事が始まります。着工前には、近隣への挨拶回りや地鎮祭などを行いますが、自分の希望次第では立ち合いや実施の有無を選ぶことができます。
⑫竣工・引き渡し・入居
建物の新築工事が完了したら、完成後の立会いで建物チェックを行います。ハウスメーカーと建物を見て回り、不具合や目立つキズが見つかった場合は、ハウスメーカーが補修・交換等の対応をしてくれます。
建物の引き渡しを終えたら、自分の好きなタイミングで引っ越しを行います。入居後の住民票を金融機関に提出しなければいけない場合があるため、その場合は忘れずに提出しましょう。
まとめ
この記事では、ハウスメーカーと工務店の違いをはじめ、ハウスメーカー選びで重要なポイントやハウスメーカー選び~入居までの流れを解説しました。家づくりで失敗しないために、家づくりの全体的な流れを把握した上で、自分に合ったハウスメーカーを選ぶよう心掛けましょう。
自分に合ったハウスメーカーを選ぶためには、ハウスメーカーや工務店といった分類はあまり左右されず、予算と希望の両方を満たす注文住宅会社を選ぶことが重要です。まずは総予算を明確にし、自分が建物に求める要素に合ったハウスメーカーに絞り込んでいくことで、効率的にハウスメーカーを探すことができます。また、土地と建物の予算の割合を考えずに話を進めてしまうと、後々行き詰ってしまうことも考えられるため、土地予算と建物予算を明確にした上で土地探しを始めるようにしましょう。
土地を選ぶ際は、基本的な建築基準法等の法令を理解しておかないと、理想の建物を建てることができない可能性があります。家づくりにおいて、土地探しはとても重要なポイントといえるため、建物のことだけではなく、土地探しのことも相談できるハウスメーカーを選ぶことが重要です。
















